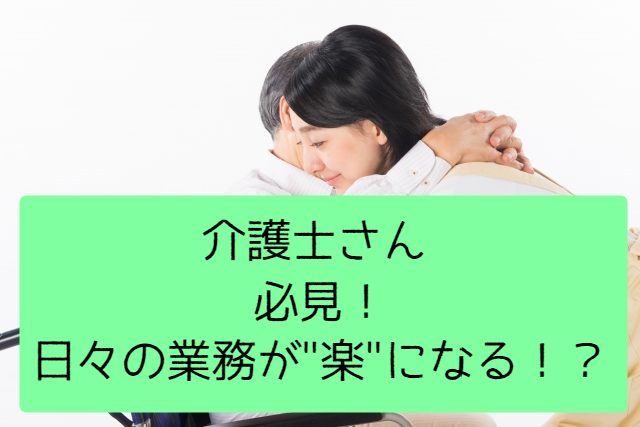
余計な力を必要とせず、最小限の力で行なうことのできる
介護技術「ボディメカニクス」。
7つの基本原理を理解したうえで介護を実践すると、日々の介護負担を軽減できるのです。
この記事では、ボディメカニクスの基本原理やポイントと合わせ、
介護に役立つ具体的な活用例をご紹介いたします。
人間の体は、筋肉や骨、関節それぞれが作用しあってさまざまな動作が可能になります。
「ボディメカニクス」とは、それらの相互作用を活用し、最小限の力で行う介護技術です。
ボディメカニクスを使えば、今まで力が必要だと思っていた介護も楽に行うことができます。
介護者の悩みである腰痛予防につながることもポイント。
介護士はもちろん、自宅で家族を介護・看護をする方にとっても大変役立つ介護技術なのです。

ボディメカニクスの活用は介護する側だけでなく、される側にとっても有意義であることがポイントです。
ボディメカニクスを活用すると、要介助者に負担の少ないスムーズなケアが可能になります。
また、介助される側の機能も活用するため、残存機能の衰えを防ぐ効果も期待できます。
実際にボディメカニクスを活用してみると、介助者と要介助者、それぞれのわずかな力で介助が楽になることを実感できるでしょう。
高齢者の介護度が高いほど直接体に触れる機会が多くなります。
ベッドからの起き上がり、車いすへの移乗、トイレを利用する際の衣服の上げ下ろしなど、生活の中で身体介護が必要になるシーンは実にさまざまです。
高齢者が寝たきりの場合には、中腰の姿勢でおむつ替えをする必要もあるでしょう。
身体介護は介護者にとって負担が大きく、とくに中腰の姿勢は腰痛の原因にもなります。
一方、ボディメカニクスを活用すれば少ない力で介護が可能となるため、
体に余計な負担がかかりません。
自宅で介護する方にとっても、毎日の身体的負担が軽減されることは大きなメリットとなるでしょう。
スムーズな介護が可能となるボディメカニクスの活用は、安全なケアにつながります。
介助される側の負担も軽減されるため、安心してケアを受けることができるでしょう。
また、前述したように、ボディメカニクスは介助者・要介助者双方にメリットをもたらす介護技術です。
声をかけあい意思疎通をはかりながら介護をすることで、お互いの信頼関係もより深まっていくでしょう。

前述したようなメリットを生み出すためには、
ボディメカニクスの基本原理をしっかりと理解する必要があります。
ここからはボディメカニクスの7つの基本原理とともに、
それぞれのポイントについて確認していきましょう。
「支持基底面積」(しじきていめんせき)とは、
転倒しないために必要な体を支える床面積のことです。
この面積は床に触れている部分だけではなく、両足間すべてを意味します。
理想的な支持基底面積をとるためにも、
介助時は肩幅くらいに両足を開くように心がけましょう。
さらに力が必要な場合には、
前後・左右の対角線上に足を開くと安定感をアップさせることができます。
両足を開くこととセットで覚えておきたいのが、
膝を曲げて体の重心位置を低くキープすることです。
床に落ちた物を拾うときにも、膝をまっすぐ伸ばした状態よりは曲げた方が楽ですよね。
同様に、介護動作も膝を曲げて行うことで重心が下がり、
安定感が増すだけでなく腰にかかる負担を軽減できます。
要介助者の身体に触れる身体介護は、
なるべくお互いが密着し重心を近づけることがポイントです。
両者の安定感が増すことで、要介助者も残存機能を活用しやすくなります。
ベッドから車いす、車いすからトイレの便座など、要介助者の身体を動かすときは水平移動が基本です。
ものを上に持ち上げる動作は重力に逆らうことになるため、余分な力が必要になります。
一方、水平にスライドすれば最小限の力で移動が可能となるのです。
体を上下すると要介助者の負担にもつながるため、
介助の際は常に水平移動を心がけましょう。
てこの原理とは、
支える部分(支点)・力を加える部分(力点)・加えた力が動く部分(作用点)の関係を利用し、弱い力で重たいものを動かす原理です。
起き上がりを介助する場合は、要介助者のひじやひざ、おしりを支点にすれば、遠心力を利用してスムーズに介助できます。
同じ重さであっても、より小さなものの方が動かすときの負担は軽減できますよね。
介助のときも、要介助者にはなるべく体を小さくまとめてもらいましょう。
具体的には、腕は伸ばしたままではなく胸の前で組んでもらいます。
可能であれば、ひざも曲げてもらうとより負担を軽減できます。
いずれも痛みのない範囲で行うように気を付けましょう。
身体介助はひとつの筋肉だけでなく、腕や腰、背中、足など体全体を使って行うように心がけます。
また体をねじらないよう、平行をキープすることも大切。
無理な姿勢は負担が大きく、腰痛の原因にもなるので気を付けましょう。

ここからは、介護現場で役立つボディメカニクスの活用例についてご紹介いたします。
在宅介護でもすぐに役立つ介護技術なので、
必要なシーンと照らし合わせながらチェックしてみてください。
車いすや椅子、便座などに座った状態から立ち上がるときには
「重心移動」を意識しながらボディメカニクスを活用しましょう。
人はつま先がひざより前にあると、座った状態から立ち上がることができません。
そのまま介助者の力だけで引き上げようとすると要介助者の負担となるため、
まずはつま先の位置をひざまで引いてもらうように声かけをしましょう。
少し足を開いてもらうとより安定感がアップします。
要介助者の腕全体を下から包み込むように支えます。
要介助者には、介助者の二の腕あたりを持ってもらうとより安定感が増します。片側に麻痺のある方の場合には、麻痺がない側の手のひらと腕を支え、お互いの体を密着させます。
要介助者に、頭をさげながらおじぎの姿勢をとってもらいます。
自然とお尻が持ち上がる状態になり、立ち上がりが楽になります。
声をかけながら、要介助者がひざを伸ばすタイミングに合わせて前へと引き上げます。
上へ引っ張るのではなく、水平に重心を移動させるように心がけましょう。
ベッドからの起き上がりを介助するときには、体をなるべく小さくまるめ、てこの原理を活用したボディメカニクスを意識します。
要介助者と体が離れていると、腰への負担が大きくなります。まずは介助しやすい高さにベッドを調整しましょう。
小さな力で介助できるよう、要介助者に体を小さくまるめてもらいます。体に痛みのない範囲で行ってもらうように気を付けましょう。
仰向けの状態から、おへそのあたりを見てもらうように声かけをします。首から肩のあたりが自然と浮き、起き上がやすくなります。
首~肩の浮いた隙間とひざの下に腕を入れます。首だけに負担がかからないよう、首から肩全体を支えるのがポイントです。
お互いの重心をそろえるイメージで体を近づけます。
この場合、支点となるのは要介助者のおしりとベッドの接地面です。
その状態からてこの原理を利用し、
遠心力を使って声をかけながら身体を起こします。
寝たきりの高齢者の介護には、
おむつ替えや着替え以外にも、褥瘡予防のための体位変換が必要です。
ベッド上の体位変換は、身体を小さくして重心を近づけることがポイントです。
腰に負担がかからないよう、作業しやすい高さにベッドの高さを調節します。
要介助者に体を小さくまるめてもらいます。
少ない力で体位変換でき、要介助者の負担軽減にもつながります。
痛みのない範囲で頭を寝返り側へ向けることで、重心が寝返り側へと移動します。
要介助者に体を近づけ、膝と肩を支点にゆっくりと寝返り側に体位変換を行います。
車いすの乗り降りは、身体的負担が大きい移動ですが、
安全性が求められる介助です。
支持基底面積を広くとりしっかりと重心を下げることに加え、
体を密着させ水平移動を心がけることがポイントです。
よりスムーズに移乗できるよう、ベッドの高さを車いすよりもやや高い位置に調整します。
要介助者の足裏が床から離れてしまうと、転倒リスクが高まります。
要介助者の足元にも注意しましょう。
ブレーキをかけ、フットレストを上げた状態で車いすを準備します。
片側に麻痺がある方の場合には、麻痺のない側に車いすをつけるのが基本です。
ベッドに座っている状態の要介助者のおしりの部分を支えながら、
身体を少しだけ前に引き出します。
立ち上がりやすいよう、つま先は膝の位置まで下げてもらいましょう。
身体が倒れてしまわないように、ベッドのサイドバーか介護者の肩を持ってもらいながら行います。
足を前後に開き、片足を要介助者の足の間に入れます。
支持基底面積を広くとり、しっかりと重心を落とすように心がけます。
要介助者の背中を抱えながら体を近づけます。
要介助者の腕は可能な限り肩に回してもらいましょう。
声をかけながら、車いすに近い方の足を軸に車いすへ移動します。
上へ持ち上げるのではなく、
水平にスライドするイメージで介助するのがポイントです。
座った位置が浅い場合には、深く腰かけるよう声かけをします。
自力で調整できない場合には後ろへまわり、要介助者の両脇に腕を入れて、
前かがみになってもらった状態から後ろへと引き寄せましょう。
座面が安定したことを確認後、フットレストに両足を乗せます。

ボディメカニクスを活用することにより、事故のリスクも軽減され、
安心安全なケアへとつながります。
介助者と要介助者それぞれにメリットをもたらす介護技術ですので、
ぜひボディメカニクスのスキルを身につけましょう。
介護士として働く方はもちろん、在宅介護をする方にとっても、
負担なく元気で介護を続けられることが大切です。
介助者・要介助者が笑顔になれるより良いケアを目指しましょう。
(c) 2026 LIKE Staffing, Inc.