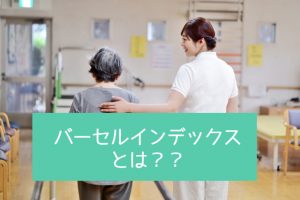
近年、介護業界で「バーセルインデックス」という生活動作の評価法が注目を集めています。
今回はバーセルインデックスの意味や、評価対象となる10の項目についてわかりやすく解説していきます。
介護業務におけるメリットやデメリットなど、ぜひ参考にしてください。

バーセルインデックスとは、アメリカで開発されたADLの簡易的な査定方法です。
ADLとは、日常生活に必要な動作を意味します。
ベッドや布団から起き上がる動作や、座る、食べるといった、毎日の生活に必要な基本動作です。
バーセルインデックスも、日常生活に必要な10の動作項目からADLを査定します。
平成30年より、介護報酬には新たに「ADL維持加算」が加わることになりました。
これは、通所介護を利用する方のADLが維持向上した場合、新たな加算が認められるものです。
これからの超高齢社会において、高齢者の自立を支援し、要介護状態を防ぐことを目的としています。
平成元年度のADL維持加算の取得施設数は、642施設です。
これは、全体の1.49%にあたります。
平成2年度の算定施設数は、1,024施設。1年間で、約1.5倍以上の通所施設が算定加算を取り入れたことになります。
また、通所介護でリハビリテーションを取り入れた利用者のADL改善度は、リハビリをしない利用者の約1.5倍です。
自立支援や介護予防の観点から見ても、通所介護施設におけるADL改善度は今後重視されていくと考えられます。

バーセルインデックスは、ADLに関する項目を全部で10項目評価します。
各項目は、0~15点まで5点きざみで評価するのが特徴です。
結果は、100点を満点に、20点ごとに5段階評価します。
バーセルインデックスは、「できるADL」を基本に動作評価をします。
「できるADL」とは、誰もいなくても安全に動作できる自立度のことです。
そのため、利用者の方の最大限の能力を、客観的に判断できます。

バーセルインデックスでは、「介助が必要ない自立」、「一部介助が必要」、「すべての動作に介助が必要」といった状態を目安に、各動作を評価します。
評価項目は全部で10種です。
介助が必要であるか、自分ですべて食べきれるかを基準にADLを評価します。
介助の必要性により、0~10点まで点数を付けます。
車いすからベッドに移る動作を4段階評価します。
介助なしで移乗できる状態は自立とみなされ、15点です。
ブレーキを固定したり、フットレストを上げ下げしたりと、移乗には一連の動作が必要です。
自立評価には、これらを自分で適切に管理できることも含まれています。
以降、声かけや介助が必要な状態に応じ、0~5点で状態を評価します。
日常生活には、身なりを整える「整容」を欠かすことはできません。
男性であれば、髭そりも整容にあたります。
朝の洗顔、歯磨きも日常生活に欠かせない動作であると言えるでしょう。
バーセルインデックスでは、すべて自分でできる状態を5点と評価します。
一部でも介助が必要であれば点数はつかず、評価は全2段階です。
トイレ動作は、0~10点で評価します。
もっとも評価の高い10点の状態は、排泄に関する介助は必要ありません。
ポータブルトイレを使っている場合は、自分で洗浄できることも意味しています。
入浴は、介助の有無によって2段階に評価します。
服を脱ぎ浴室に移動し、身体を洗うなど、入浴にはさまざまな行為が必要です。そのため、見守りが無くても安全に入浴できる状態は、自立度も高いと言えるでしょう。
距離や歩行状態で0~15点まで4段階評価します。
自立歩行には補装具、介助歩行には歩行器を使用することが可能です。
自力で車いすを使用できない場合や、車いすで45m以上歩行できない場合には点数はつきません。
階段の昇り降りは、足腰の弱った方にとって不安要素の大きな動作ですよね。
バーセルインデックスでは、「できるADL」を重要視します。
そのため、自立判定にはただ昇り降りできるだけでなく、見守りが必要ないことがポイントです。
歩行状態に不安があり、第三者の見守りが必要な場合は5点。
階段の昇り降りができない状態には、点数はつきません。
衣服だけでなく、靴の脱ぎ履きなども含めて評価します。
服にファスナーが付いている場合には、上げ下ろしも評価基準です。
サポーターなどの装具を着用している場合も、自分で着脱できることが自立の目安となります。
排便コントロールの状態を、浣腸や座薬が使用できることも含めて評価します。失禁のない状態は10点です。
失禁のある状態は5点、どちらにも当てはまらなければ0点となります。
失禁コントロールの状態を評価します。
失禁がない場合は、収尿器の取り扱いができることも含めて10点です。
排便コントロールと同様に、失禁のある状態は5点、それ以外のケースには点数はつきません。

今までにない評価法を取り入れる際は、そのメリットも気になりますよね。
10項目の評価内容をふまえた上で、メリットについて確認していきましょう。
各項目を5点ずつ評価するバーセルインデックスは、客観的な評価がしやすい査定方法です。
そのため介護士だけでなく、家族や医療関係者も利用者の方の自立度を把握しやすくなります。
たとえば、「歩行状態が改善した」と言われても、具体的な状態をイメージするのは難しいですよね。
バーセルインデックスでは、歩行距離と歩行器の有無によって状態を点数化するため、誰もが自立度を認識できます。
利用者の方にとっても、自分の自立度を把握できるのは大きなメリットです。
はっきりとした目標を持ったうえで、リハビリに取り組むことができるでしょう。
バーセルインデックスは、各項目の評価基準がシンプルなことが特徴です。
記録や査定に時間や手間がかからないこともポイントです。
忙しい介護業務の間にも、利用者の方の身体状況を評価することが可能です。
チームワークで情報をやり取りするときにも、表記がシンプルで分かりやすいことは大きなメリットとなるでしょう。
前述したように、バーセルインデックスでは「できるADL」を評価します。
つまり、バーセルインデックスの査定は、利用者の方の最大限の能力を評価した結果であると言えるのです。
それぞれの項目を比較検討することによって、今現在できない項目も、リハビリによって「できるADL」へと改善できる可能性もあります。
利用者の方がどの動作に困難を感じているのか、どのようなリハビリが必要なのか見出せるのも、バーセルインデックスのメリットです。
1955年にアメリカで使われ始めたバーセルインデックスは、世界で広く普及しています。
介護業界だけでなく、医療や福祉業界などでも幅広く使われる手法です。
そのため、国外にも評価基準が通じるというメリットがあります。

バーセルインデックスは、客観的なADL評価が可能となるシンプルな査定方法です。
介護業界で注目されるバーセルインデックスには、どのようなデメリットが考えられるのでしょうか。
日常生活の基本動作を評価することが、バーセルインンデックスの大きな特徴です。
そのため、IADLと呼ばれる手段的日常生活動作の評価ができません。
手段的日常生活動作とは、買い物や電話、金銭管理といったより複雑な生活動作です。
たとえば、ADLである歩行が可能あっても、金銭管理ができなければ、買い物をすることはできないでしょう。
つまり、バーセルインデックスの評価だけでは、利用者の方の具体的な日常生活は判断できないケースもあるのです。
このデメリットを補うためには、実際の動作や介助について記録し、情報共有する必要があります。
特に日常的に繰り返す動作については、点数よりも高い力を発揮することもあるため、必要に応じたサポートを心がけましょう。
バーセルインデックスの評価はシンプルで記録しやすいものの、細かい変化が分かりづらいというデメリットもあります。
たとえば、車いすの方が歩行器での歩行が可能になるまでには、徐々に段階を踏んでいかなくてはいけません。
バーセルインデックスの評価では、その変化を記録することはできないのです。そのため、急に点数が上がったり下がったりするケースも考えられます。
バーセルインデックスでは「全介助」「要介助」のように状態を評価しますが、必要な介助は利用者の方の身体状況に応じて異なります。
動作によっては、要介助にあたるのか迷ってしまうこともあるでしょう。
そのため、詳細な身体状況までは分かりかねるというデメリットが生まれる可能性があります。
バーセルインデックスは、世界共通のADL評価方法です。
記録方法がシンプルで分かりやすく、他職種とも情報を共有しやすいというメリットがあります。
一方、詳細な身体状況を記録できないことは、デメリットのひとつです。
より具体的なケアにつなげるためには、足りない部分を補いつつ活用する必要があります。
バーセルインデックスを上手に取り入れながら、高齢者一人ひとりに応じた自立をサポートしていきましょう。
(c) 2026 LIKE Staffing, Inc.